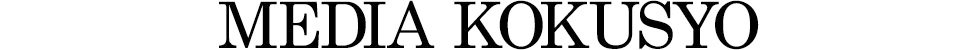読売新聞押し紙訴訟 福岡高裁判決のご報告 ‐モラル崩壊の元凶「押し紙」‐
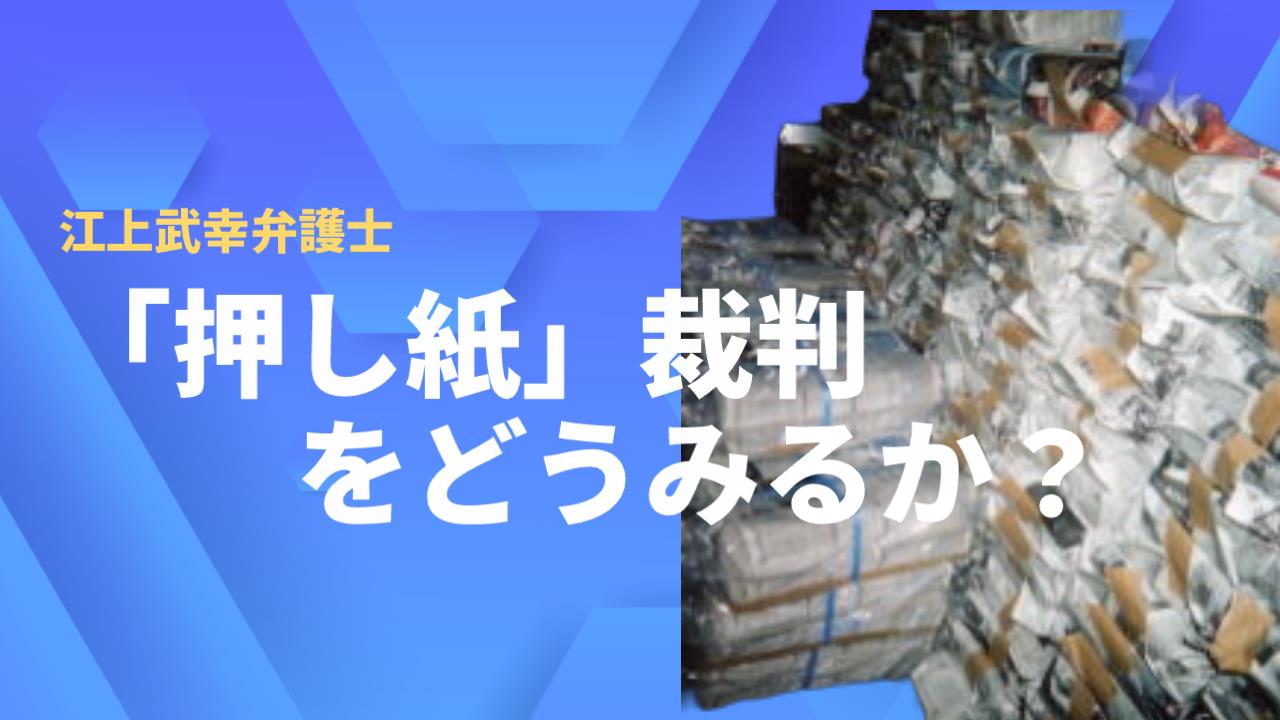
福岡・佐賀押し紙訴訟弁護団 弁護士・江上武幸(文責)
2024(令和6年)5月1日
長崎県佐世保市の元読売新聞販売店経営者が、読売新聞西部本社に対し、押し紙の仕入代金1億5487万円(控訴審では、金7722万に請求を減縮)の損害賠償を求めた裁判で、4月19日、福岡高裁は控訴棄却の判決を言い渡しました。
* なお、大阪高裁判決の報告は、2024年4月13日(土)付「押し紙の実態」に掲載されていますのでご一読ください。
「バブル崩壊の過程で、私たちは名だたる大企業が市場から撤退を迫られたケースを何度も目の当りにしました。こうした崩壊劇にはひとつの共通点があります。最初はいつも小さな嘘から始まります。しかし、その嘘を隠すためにより大きな嘘が必要になり、最後は組織全体が嘘の拡大再生機関となってしまう。そして、ついに法権力、あるいは市場のルール、なによりも消費者の手によって退場を迫られるのです。社会正義を標榜する新聞産業には、大きな嘘に発展しかねない『小さな嘘』があるのか。それともすでに取り返しのつかない『大きな嘘』になってしまったのでしょうか・・・・。」(新潮新書2007年刊・毎日新聞元常務河内孝著「新聞社破綻したビジネスモデル」の「まえがき」より)。
大阪高裁と福岡高裁の判決をみると、裁判所は平成11年の新聞特殊指定の改定(1999年)を機に、押し紙については黙認から積極的容認に姿勢を転じたように見受けられます。
 今回の福岡高裁判決の「当裁判所の判断」部分は、わずか2頁にすぎません。しかし、頁数が極端に少ないため、かえって裁判所の押し紙問題についての基本的立ち位置や考え方がわかりやすくなっています。以下、とりあえず福岡高裁判決を読んだ感想を述べさせていただきます。
今回の福岡高裁判決の「当裁判所の判断」部分は、わずか2頁にすぎません。しかし、頁数が極端に少ないため、かえって裁判所の押し紙問題についての基本的立ち位置や考え方がわかりやすくなっています。以下、とりあえず福岡高裁判決を読んだ感想を述べさせていただきます。
新聞社の社会的影響力と広告媒体力は発行部数によって決まります。新聞社は、発行部数を大きくするために、優越的地位を背景にして販売店に対し実配数を超過する新聞(以下、「押し紙」といいます。)を仕入させようとします。販売店は新聞社の意向に逆らうことが出来ませんので、押し紙を引き受けざるを得ません。新聞社にとって、押し紙は販売店への売上増に直結しており、紙面広告単価を高く設定することができ、社会的影響力も大きくできるという一石三鳥のメリットがあります。しかし、販売店にとっては、廃棄するか無代紙・サービス紙として無償配布するかしかない無駄な新聞です。
そのため、新聞社は販売店に押し紙を仕入れさせるために、押し紙にも折込広告収入が得られるようにしたり、不足分は補助金を支出するなどの施策を講じています。このような押し紙を中核に据えた新聞経営のことが「新聞社のビジネスモデル」と呼ばれるものです。
読売新聞1000万部・朝日新聞800万部・毎日新聞300万部といわれた時代がありましたが、その内、実際に配達される新聞がいかほどあるかについては公表されていません。表向きは販売店の実配数を新聞社が知らないことにされていますが、実際は、大量の押し紙が含まれていることを世間に知られないようにするための嘘です。小さな嘘ではなくとてつもなく大きな嘘です。
これまで、日本新聞販売協会・公正取引委員会・ABC協会などの公的組織によって押し紙の調査が為されたことがありますが、正確な部数や割合は不明なままでした。その後、押し紙訴訟や折込広告料返還訴訟が提起されるようになり、本ブログの主催者である黒薮哲哉さんのもとに販売店経営者から多くの内部資料が寄せられるようになったことから、次第に押し紙の部数や割合が明らかになってきました〔黒薮哲哉著・「新聞と公権力の暗部-押し紙問題とメディアコントロール-」(鹿砦社刊)参照)〕。
* ネットで「押し紙」を検索していただければ、大量の新聞や折込チラシが古紙回収業者のトラックに積み込まれている現場の様子を見ることができます。
押し紙は、1955年(昭和30年)の独占禁止法新聞特殊指定の制定によって禁止されるようになり、1964年(昭和39年)と1999年(平成11年)の二度の改正を経て現在に至っています。新聞の発行部数は、人口の高齢化と少子化・景気の悪化・ネット社会の普及などの様々な要因で、2000年(平成12年)の5370万部から23年後の2023年(令和5年)には2860万部と約半分近くまで減少しています。このままでいけば、10数年後には発行部数がゼロになるような減少スピードです。
元朝日新聞東京本社販売局管理部長の畑尾一知氏は「新聞社崩壊」(新潮新書・2018年(平成30年)発行)に、「今の新聞社は薄氷の上を渡るソリのようである。ソリの水没は避けられないものだろうか。」との現状認識を示した上で、「紙の新聞には今でも数十パーセントの支持率があり、今は年々減っているとはいえ、新聞自体が生まれかわれば過去の支持者が戻ってくるはずである。新聞社は亡んでも新聞は生き残り得る。」との希望的観測を述べていますが、果たして新聞は生き残ることが可能でしょうか。大いに疑問です。
畑尾氏は、「権力側にとって不都合な情報を公開されたくないのは、ごく自然なことである。情報の公開度は大衆の支持を背景にジャーナリズムがどれだけ頑張るかにかかっている。パリに本部を置く『国境なき記者団』の報道の自由度ランキングの2016年(平成28年)の日本のランキングは72位だった。年々ランクを下げ先進諸国の中では最低に位置している。第二次安倍政権(注:2012年(平成24年)12月~2020年(令和2年)9月まで)になってからは、政権基盤の強化がますます進むのに対し、新聞やテレビは購読者・視聴者が減っていくに連れて、弱体化が顕著になっている。不都合な事実を隠したい権力側の圧力はますます強くなっていくだろう。」と書いています。
また、「2014年(平成26年)に神戸新聞が兵庫県議会議員の政務活動費不正使用問題を発掘し報道したのがきっかけで、各新聞社が全国の地方議会における議員の政務活動費の使途について調査し、多くの不正が発覚した。」との記載もありました。この箇所を読んでいて、新聞は、国会議員の裏金問題については、何故、目を向けなかったのだろうか、何故、調査しなかったのだろうかという疑問にとらわれました。
黒薮さんのブログに、2006年(平成18年)の参議院予算委員会で、当時の安部晋三国務大臣が押し紙問題について国会答弁をしていることが紹介されており、安倍氏が新聞社の押し紙問題を新聞経営陣の取り込みに利用したのではないかと考えるようになりました。
また、安倍内閣発足以降、自民党政権がテレビの報道番組に次々と圧力を加えるようになり、政権批判の有力なコメンテーターが次々と番組から降板していきましたが、その背後にもテレビ局の親会社である新聞社の押し紙問題が隠されていたのではないかとの疑念をもつようになりました。
 黒薮さんは、1999年(平成11年)の新聞特殊指定が改訂された年に、特に着目したいと述べられております。今後の調査および報道に期待しているところです。
黒薮さんは、1999年(平成11年)の新聞特殊指定が改訂された年に、特に着目したいと述べられております。今後の調査および報道に期待しているところです。
冒頭に紹介した毎日新聞元常務の河内孝氏の著書に、1981~82年(昭和56~7年)当時、読売新聞の巌専務取締役販売局長だった丸山巌氏(渡邉恒雄氏と次期読売社長のライバル候補と目された良識ある方です。)の、「本社(読売新聞社)が販売店に送りつける押し紙で、配達もされずに梱包のまま残紙屋に回収される残紙が、なんと年間300億円にもなる。こんな無駄が許されるわけがない」との発言と、朝日新聞の販売担当常務取締役の古屋哲夫氏の、「内部努力ではもうだめ。公権力が入ってこざるを得ない。そこまで販売乱戦の危機は深刻化している。これが最後のチャンス」との発言が記載されています。
この時期に、両氏のような良識ある大手新聞社の役員クラスが、一致結束して押し紙の廃止に取り組んでおれば、報道の自由度ランキング世界第72位にみるような新聞が政治権力に取り込まれる惨憺たる状況にはならなかったのではないかと思います。朝日に追いつけ追い越せの大号令のもと、1000万部体制を目指して、なりふり構わず部数拡張路線を突っ走ってきた経営者の罪の大きさを実感します。
黒薮さんは、「新聞と公権力の暗部」で、旧統一協会による霊感商法の被害額が35年間で1237億円であるのに対し、押し紙による被害金額は32兆6200億円に及ぶとの試算を示しておられます。
新聞各社は、国有地の払い下げや、第3種郵便物・再販制度・消費税の軽減税率の適用、あるいは記者クラブ室の提供など様々な優遇措置を受けているだけでなく、戦後の読売新聞と朝日新聞の最高責任者は、いずれもアメリカの協力者(手先・スパイ)だったことが米国の公文書で明らかになっています。従って、日本の新聞社は本来の意味でのジャーナリズム精神はそもそも持ちあわせていなかったのではないかとの疑念があります。ソビエトや中国、あるいは軍事独裁政権の例を持ち出すまでもなく、新聞やテレビは本来に国家権力機構の一部であると割り切ってしまえば、わが国で、押し紙が政治権力によって見逃され、マスコミ統制の道具に利用されてきたとしても不思議ではありません。
しかし、以前は、経営と記事は別物だと割り切り、憲法の保障する国民の知る権利を実現するために取材活動に命をかけていた記者がたくさんいたように思います。朝日新聞阪神支局の若い記者が何者かによって殺害された衝撃的事件のことは、宣明に記憶しています。
しかし、押し紙問題が販売局以外の編集部の記者達にも知られるようになり、押し紙により高収入を得てきたことを知った時、真からの正義感に燃えて権力の不正を追及する取材・報道に専念することが果たして出来るのか、はなはだ疑問です。新聞社の経営と自らの家族と生活の生殺与奪の権が、権力に握られていることを知った時、記者のメンタルにどのような影響を及ぼすか、想像に難くありません。
本来、押し紙判決の言渡しの期日には、記者席には新聞記者が満席状態で座っていてしかるべきですが、記者席には新聞記者の姿は一人もいないのが現実です。もちろん、押し紙問題について新聞やテレビが取り上げることもありません。
 日本新聞協会の公正取引協議委員会は、「モデル細則」を策定して、全国11地区の地区公正取引協議会に、「押し紙」の具体的定義を示して押し紙の自主解決の徹底をはかろうとしたことがあります。公正取引委員会もこの取組を全面的にバックアップする姿勢を示しました。1985年(昭和60年)頃のことです。
日本新聞協会の公正取引協議委員会は、「モデル細則」を策定して、全国11地区の地区公正取引協議会に、「押し紙」の具体的定義を示して押し紙の自主解決の徹底をはかろうとしたことがあります。公正取引委員会もこの取組を全面的にバックアップする姿勢を示しました。1985年(昭和60年)頃のことです。
平成9年に北國新聞社が販売店にあらかじめ注文部数を指示して押し紙禁止規定の脱法行為をはかるという事件が発生しました。この事件について、公正取引委員会は史上初めて押し紙の本格的調査を行い、同社に排除勧告を発令します。ちなみに、公取委が押し紙の排除勧告を発令したのは、後にも先にもこの時の一回だけです。
北國新聞の押し紙事件については、インターネットで検索してもらうことにして、公取はこの事件をきっかけに、何故か、それまでの新聞業界による押し紙の自主規制(予備紙2%の自主的ルール)を免除する方針に転換します。その結果、新聞社は相互監視の役目を放棄し、他社の目を気にすることなく、予備紙2%自主ルールに反し、予備紙を際限なく増やしていくようになります。
更に、公取委は平成11年告示を改正し、従前の「注文部数を超えて」の文言を「注文した部数を超えて」という文言に変更します。この文言の変更の意味、経過については、別稿で報告することにします。
北國事件を契機とする公取の押し紙禁止規定の取り締まり方針の大転換の表向きの理由は、押し紙の規制を新聞業界の自主性に委ねていたのではいつまでも解決出来ないので、爾後、公取委が直接厳しく取締に乗り出すことにするというものです。
しかし、公正取引委員会の人員や予算の規模からして、全国100社を超える新聞社とその系列の販売店の押し紙問題を公取委の力で解決するのが出来ないことは歴然としています。公取委がこの方針転換は、新聞社に対し押し紙問題は今後不問にすることを宣言したに等しいものです。
平成11年告示の「注文部数」の文言の改定の結果、裁判所は「新聞社が販売店の注文した部数を超える新聞を供給しなければ、注文した部数にどれだけの予備紙が含まれていようとも押し紙にはならない」との解釈をとることが出来ようになりました。
長々と、述べてきましたが、今回の福岡高裁と大阪高裁の判決は、新聞業界が自主的に決めた予備紙の上限規制2%のルールについて、平成11年告示改正により撤廃され法的拘束力を失ったとの判断を示し、仮に、実配数1000部の販売店が2000部あるいは3000部、論理的には1万部の新聞を注文した場合でも、新聞社がその部数を越えて新聞を供給しない限り押し紙には該当しないという立場に立つことを明言しています。独禁法新聞特殊指定の押し紙禁止規定を事実上廃棄するに等しい判断です。
最高裁判所の違憲立法審査権はともかくとして、下級裁判所には、法令の廃止に等しい法律解釈を行う権限はないにもかかわらず、地裁・高裁を問わず、押し紙の敗訴判決を下した裁判官はみな等しくこのような法令解釈を採用しています(注:もちろん、そのような裁判官ばかりではありません・・・)。
今般の自民党国会議員の「裏金問題」に端を発した衆議院の補欠選挙における自民党の全敗は、日本社会の根底からの地殻変動を予感させる出来事です。
将来に希望を失わず、正義感にあふれる裁判官との出会いを楽しみに、今後も押し紙裁判を続けていきますので、引き続きご支援とご協力のほどをよろしくお願いします。
草々
読売「押し紙」裁判、福岡高裁判決、元店主の控訴を棄却、判決文に「押し紙」問題を考える上で興味深い記述

福岡高等裁判所の志賀勝裁判長は、4月19日、読売新聞の元販売店主が起こした「押し紙」裁判の控訴審で、元店主の控訴を棄却する判決を下した。
去る3月28日には、大阪高裁がやはり元店主の控訴を棄却する判決を下していた。これら2つの裁判の判決には、勝敗とは無関係に、はからずも裁判官の筆による興味深い記述が確認できる。それは新聞特殊指定の解釈に言及した部分で、その記述を読む限り、1999年7月に改正され,現在施行されている新聞特殊指定の下で新聞社は、旧バージョンの新聞特殊指定よりも、はるかに「押し紙」政策を実施しやすくなった事を露呈している。
◆◆
1999年7月の新聞特殊指定の改正は、北國新聞で「押し紙」問題が発覚したのを受けて、日本新聞協会と公取委が折衝を重ねた末に決定・実施されたものであるが、それにもかかわらず「押し紙」がより容易になる方向性で改訂されているのだ。その奇妙な事実を、はからずも志賀勝裁判長の判決文が立証したのだ。
ちなみにこの時期に総理の座にいたのは、自民党新聞販売懇話会・会長の座にいた小渕恵三氏である。日本新聞協会の会長は渡邉恒雄氏だった。また、公取委の委員長は、なぜか後に日本野球機構コミッショナーに就任する根來泰周氏(写真、出典:スポニチ、Wikipedia)である。
日本新聞協会と公取委の話し合いの記録については、わたしが情報公開請求を申し立てたことがあるが、黒塗りになって開示された。この黒塗りの部分に、日本の新聞社の闇が隠されている可能性が高い。
詳細については後日、報告する。
なお、この裁判にも自由人権協会代表理事の喜田村洋一弁護士が読売の代理人として名を連ねている。
読売新聞「押し紙」裁判控訴審、販売店が敗訴するも判決文の中で新聞業界の商慣行が露呈

新聞販売店の元店主が「押し紙」(広義の残紙)により損害を受けたとして損害賠償を求めた裁判の控訴審(約6000万円を請求)で、大阪高裁は3月28日、元店主の控訴を棄却した。
「押し紙」というのは、ごく簡単に言えば残紙のことである。(ただし、独禁法の新聞特殊指定が定義する「押し紙」は、「実配部数+予備紙」を超える部数のことである)。
元店主は、2012年4月にYC(読売新聞販売店)を開業した。その際、前任の店主から1641部を引き継いだ。ところが読者は876人しかいなかった。差異の765部が残紙になっていた。このうち新聞の破損などを想定した若干の予備紙を除き、大半が「押し紙」となっていた。
以後、2018年6月にYCを廃業するまで、元店主は「押し紙」に悩まされた。
大阪地裁は、元店主が販売店経営を始めた時点における残紙は独禁法の新聞特殊指定に抵触すると判断した。前任者との引継ぎ書に部数内訳が残っていた上に、本社の担当員も立ちあっていたことが、その要因として大きい。
控訴審の最大の着目点は、大阪高裁が読売の独禁法違反の認定を維持するか、それとも覆すだった。大阪高裁の長谷部幸弥裁判長は、大阪地裁の判断を覆した。
その理由というは、元店主の長い業界歴からして、「新聞販売に係る取引の仕組み(定数や実配数、予備紙や補助金等に関する事項を含む)について相当な知識、経験を有していた」ので、従来の商慣行に従って搬入部数を減らすように求めなかったというものである。皮肉なことに長谷川裁判長のこの文言は、新聞業界のとんでもない商慣行を露呈したのである。
しかし、残紙が「押し紙」(押し売りした新聞)に該当するかどうかは、本来、独禁法の新聞特殊指定を基準として判断しなければならない。元店主に長い業界歴があった事実が、新聞特殊指定の定めた「押し紙」の解釈を変えるわけではない。この点が、この判決で最もおかしな箇所である。
新聞特殊指定では、残紙が「実配部数+予備紙」を超えていれば、理由を問わず「押し紙」である。もちろん「押し紙」のほとんどが古紙回収業者のトラックで回収されていたわけだから予備紙としての実態もまったくなかった。
◆「読売には『押し紙』は一部も存在しない」
この裁判の読売側の代理人を務めたのは、6人の弁護士である。この中にはメディア関係者から重宝がられている自由人権協会代表理事の喜田村洋一弁護士も含まれている。喜田村氏は、わたしが知る限り今世紀に入ったころから、読売の「押し紙」裁判に登場して、読売には「押し紙」は一部も存在しないという出張を繰り返してきた。
◆公権力機関に組み込まれた日本の新聞業界
今回の控訴審判決の内容から判断して、わたしは新聞業界と公権力機関の距離が極めて近い印象を受けた。今回に限らず、「押し紙」裁判の判決を読むたびに、両者は普通の関係ではないと感じる。先日の日経新聞「押し紙」裁判における最高裁の決定もそうだった。
その意味で「押し紙」裁判の提起は重要だ。たとえ販売店の敗訴であっても、判決のたびに新聞業界が公権力機関に組み込まれている実態が露呈する。「押し紙」により新聞業界が莫大な利益を上げる構図があるので、公権力機関はこの問題を泳がせておけば、新聞の紙面内容に暗黙の圧力をかけることができる。
本来、「押し紙」問題にメスを入れなければならないのは新聞記者である。自分の足もとの問題であるからだ。ジャーナリスト集団が従順な「羊の群れ」ではだめなのだ。有権者は新聞の情報を鵜のみにしてはいけない。
読売新聞押し紙訴訟 大阪高裁判決の報告
福岡・佐賀押し紙訴訟弁護団 弁護士・江上武幸(文責)
広島県福山市で読売新聞販売店を経営してきた濱中勇志さんが、読売新聞大阪本社に対し「押し紙(残紙)」の仕入代金1億1351万9160円の支払いを求めた裁判で、3月28日、大阪高裁は大阪地裁に続き請求を棄却する判決を言い渡しました。判決は大阪地裁が部分的に認定した「押し紙」の存在も取り消すという不当なものでした。独占禁止法の「押し紙」禁止規定の趣旨・目的に反する内容としか言いようがありません。
我が国の裁判官が、なぜ頑なに新聞社による「押し紙」の存在を認めようとしないのか?この疑問については、来週4月19日(金)に、福岡高裁で予定されている読売新聞西部本社を相手方とする別の「押し紙」裁判の控訴審判決の後に再考し、改めてみなさまに報告させていただくことにして、ここでは濱中さんの裁判に焦点を当て私の見解を述べてみます。
平成24年4月から令和30年6月までの6年3ヶ月間で、濱中さんが「押し紙」(業界では配達されないで店に残る新聞という意味で「残紙」と呼ばれています。)によって被った損害は1億1351万円になります。この金額は、読売新聞社が濱中さんに送付してきた部数(定数)から、真に必要な部数(実際の配達部数に適正予備紙2%を加えた部数)を引いた6万1528部に、1部当たりの仕入原価1845円をかけて算出したものです。
ちなみに、19日に福岡高裁で判決の言渡しが予定されている別の読売新聞「押し紙」裁判でも、販売店の損害額は尋常ではありません。平成23年3月から令和2年2月までの9年間で、販売店が被った損害は1億1315万円になります。
これらのケースはほんの一例にすぎません。読売新聞社全体で年間どれくらいの残紙が発生し、その被害金額がどの程度になるのかは想像もつきません。
濱中さんが訴訟にふみ切った理由は単純で、読売新聞社が対外的には「押し紙」は一部たりとも存在しないと公言してきたので、皆さんに真実を知ってもらいたいと考えたからです。
■3月28日の高裁判決
3月28日午後1時20分、私と黒薮さんの二人は大阪高裁別館7階の72号法廷の傍聴席に座っていました。読売側は黒のスーツに身を固めた社員が数名来ていました。その中に弁護士がいたかどうかは分かりませんが。
書記官から、読売の「押し紙」裁判の判決を言い渡す前に、別件の判決言渡しがあることが事前に伝えられました。
「押し紙」裁判の判決言い渡し時間が近づくと、3人の裁判官が入廷してきました。別件の判決の当事者は双方とも出頭していませんでした。私は、傍聴席の最前列に座っていましたが、別件裁判の判決言い渡しが終わったので、傍聴席から立ちあがり、控訴人席に向かおうとしました。
ところが驚いたことに、私が控訴人席につくのを待たずに、裁判長は判決文を読み上げました。控訴棄却の簡単な主文を読みあげたのです。そして3人の裁判官は、私を一瞥することもなく後ろのドアの向こうに消えました。
これまでの「押し紙」裁判で、販売店の敗訴判決を言い渡してきた裁判官たも、同じような官僚的雰囲気を身にまとっていましたが、代理人弁護士が着席する前に判決文を言い渡すような非常識な裁判官に会ったのは今回が初めてでした。
私は、司法研修所29期卒業ですので弁護士生活は50年近くになります。高裁判決を言い渡した裁判長をネットで検索したところ、研修所42期の裁判官であることが分かりました。私は5月で73歳になりますので、13期下の裁判長の年齢は60歳くらいでしょうか。私の同期・同クラスには最高裁長官や高裁長官に出世した裁判官がいますが、弁護士の着席を確認しないで判決を言い渡すなど、社会常識をわきまえない裁判官が誕生していることを、皆さんはどう思われるでしょか。
■大阪高裁判決の次の二つの大きな誤り
(1)大阪地裁が認定した「押し紙」を認めなかった誤り
読売新聞社は、濱中さんが販売店経営を始めた平成24年4月に1641部の新聞を搬入してきました。濱中さんは経営を引き継いだ最初の月だったので、自分では注文部数は決めていませんでした。搬入された部数は、読売新聞社が前経営者に対して搬入していた部数です。読売新聞社はそれと同じ部数を濱中さんに送付したのです。
この月の戸別配達数と即売数の合計は876部でした。これに2%の予備紙18部を加えた部数の894部があれば販売店経営には事足ります。その差の747部が経営に必要のない新聞です。率にすると搬入された新聞の46%になります。この部数が新聞特殊指定が禁止した「押し紙」であるというのが我々弁護団の主張でした。
平成24年(2012年)当時の読売新聞の発行部数は1000万部程度だったと思われますが、濱中さんのケースでは、開業時に搬入された部数のうち46%が残紙になっていたわけです。大阪地裁もそれを認めました。しかも、それが「押し紙」に当たるとの判断したのです。この認定を、読売新聞社は黙って見過ごすことが出来なかったのでしょう。高裁にこの部分についての判断の見直しを迫りました。
その結果、大阪高裁は読売の主張を認めて、大阪地裁の「押し紙」認定を覆す判決を下したのです。私どもが主張した1641部の送り部数の内、747部は「押し紙」であるという主張は退けたのです。しかし、販売店経営に真に必要な部数を超える747部の新聞が残紙として販売店に残っていたことは高裁も否定出来ませんでした。従って、「押し紙」は一部たりとも存在しないという読売のこれまでの対外的な発表が客観的事実と違うことは高裁判決によっても揺るぎませんでした。発行部数世界一の新聞社を誇る読売新聞社の内実がこのように惨憺たる状況にあることを裁判を通じて社会に知らせることができましたので、それだけでも濱中さんが「押し紙」裁判を起こした意味は充分あったと考えています。
(2)押し紙禁止条項の意図的な解釈の誤り
大阪地裁も大阪高裁も、平成11年改正告示の「押し紙」禁止規定の解釈について、私どもの主張を退けました。
平成11年告示の「押し紙」禁止規定は「押し紙」を、➀注文部数超過行為、➁減紙拒否行為、③注文部数指示行為の3類型に分類しています。
このうち、①の注文部数超過行為については、昭和30年・39年告示では「注文部数」という文言が使われていましたが、平成11年告示では、「注文した部数」に変更されています。
昭和30年・39年告示でいう「注文部数」とは、実配部数に2%の予備紙を加えた部数のことです。それを超える部数は「押し紙」です。必ずしも販売店が実際に注文書式に記入した部数のことではありません。
私どもは、平成11年告示でいう「注文した部数」の定義についても、昭和30年・39年告示の「注文部数」と同じく、実配部数に2%の予備紙を足した規範的意義を有する法令用語と解釈すべきであり、文言解釈によるべきではないと主張してきました。しかし、これまで「押し紙」を認めなかった裁判所では、平成11年告示でいう「注文した部数」とは、文字通り販売店が注文した部数であり、従前の規範的意義を有する「注文部数」の定義・解釈とは異なるとの判断を示すのが常でした。その結果、2%の予備紙を大幅に越える残紙であっても、それが販売店の「注文した部数」であれば、「押し紙」にはならないという解釈が可能となっていたのです。
②の「減紙拒否行為」とは、新聞社が販売店からの減紙の申出を拒否して、従前の部数を供給することです。
③の「注文部数指示行為」とは、新聞社が販売店にあらかじめ指示した部数を注文させ、その部数を供給する行為のことです。
今回の大阪地裁判決と大阪高裁判決も、平成11年告示で文言が改正された「注文した部数」とは文字通り販売店が注文した部数を意味するとの解釈を採用しました。読売は、販売店が例え2%を大幅に超える予備紙を含む部数を注文しても、新聞社は「注文した部数」をそのまま供給する販売店契約上の義務があると一貫して主張しています。つまり、新聞社は販売店が注文の書式で「注文した部数」を超えて新聞を供給さえしない限り、配達されない残紙がどれだけあっても「押し紙」にはならないという主張です。
しかし、独禁法が新聞特殊指定に「押し紙」禁止規定を設けたのは、新聞社が自社の利益をはかるため優越的立場を利用して販売店に経営に必要のない新聞を供給し仕入れ代金を支払わせて不利益を及ばすことを防ぐことを主たる目的としています。従って「注文した部数」を定義として採用すれば、新聞特殊指定の役割が果たせません。
私どもは、読売新聞社と裁判所に対し、「仮に実配数1000部の販売店が2000部あるいは3000部、極端にいえば1万部の注文をしてきた場合でも、新聞社は販売店に『注文した部数』を供給する義務があり、「押し紙」にはあたらないというのですか?」という疑問を投げかけましたが、ついにそれに対する回答は為されませんでした。
裁判所・裁判官は、平成11年告示の改正により登場した「注文した部数」の文言に着目し、昭和30年・39年告示の規範的意義を有する「注文部数」の定義・解釈と平成11年告示の「注文した部数」の定義・解釈とは異なるとの見解を示し、「押し紙禁止規定」を事実上無力化し新聞社の利益を販売店の利益に優先させる方向に舵をきりました。
■新聞社は、利益追求優先の私企業とは異なる
水俣訴訟のチッソ、塵肺訴訟の炭鉱、アスベストの製造メーカー、予防接種被害の薬剤メーカーなど、これまでも社会的に大きな非難を受けた企業が、裁判では堂々とみずからの正当性を主張してきた歴史があります。
しかし、新聞社は、これらの経済的利益追求優先の私企業と異なり、真実を追求し権力の横暴や不正をペンの力であばく社会的使命を帯びています。
昭和30年に、公正取引委員会が新聞業界の不公正な取引方法の典型である「押し紙」を新聞特殊指定を定めて禁止してから70年が経過しようとしています。しかし、今だに「押し紙」問題は解決していません。私が、裁判において「押し紙」の存在を否定し責任を争う新聞社の法廷戦術以上に問題だと思うのは、新聞社と公権力の距離の問題です。新聞社は日本の権力機構の中に組み込まれているのではないか、政治家や行政官のみならず、裁判所・裁判官によっても保護されているのではないかという危惧を抱くようになっています。つまり、新聞社が「押し紙」問題を黙認してもらうのと引換に、紙面上で権力の濫用や不正の追求が思うように出来なくされているのではないかという危惧です。
新聞記者が使命感に基づく本来のジャーナリストとしての仕事ができない環境にあるのであれば、次のような項目については新聞研究者やジャーナリストの方々に調査能力を発揮して、その背景を明らかにして欲しいものです。
① 平成11年告示の改定で、それまでの規範的意義を持つ「注文部数」という用語が「注文した部数」という文言に変更された経緯と理由、②平成9年の石川県の北國新聞の「押し紙」事件を契機に、「押し紙」禁止規定の自主規制から新聞業界が解放され、予備紙2%ルールの撤廃が行われた経緯と理由、③後日、日本プロ野球コミッショナーに就任しているこの時期の公正取委員会の委員長と、平成11年告示の改正との関係、④「押し紙」訴訟の担当裁判官の不思議な人事異動の背景等々についてです。
■「押し紙」問題の幕引きは許されない
このところメディア状況は大きく変わろうとしています。インターネットの普及で、これまで新聞とテレビが報道してこなかった国民の目から隠されてきた事実が次々と明らかにされるようになっています。たとえば、ジャニーズ事務所の性加害問題、政治家の裏金問題、小池東京都知事の学歴詐称問題などです。これらの問題が、インターネットを通じて詳しく報道されるようになっています。
戦前・戦中の新聞は、戦意高揚をあおり数百万の尊い国民の命を犠牲に追い込んだ戦争責任があったにもかかわらず、口先だけの反省で、戦後一転して米国の占領政策に協力し、現在も安保法制・安保体制を容認し、日本国民の真の独立精神の涵養には背を向けているとしか思えません。
ネット社会が隅々まで広がるのと反比例して新聞・テレビの衰退はますます進んでいます。新聞の消滅と共に「押し紙」も消滅する運命にありますので、今更、「押し紙」問題の解消を訴えても時すでに遅しとの感はしますが、昭和30年代に独占禁止法新聞特殊指定により禁止された「押し紙」を新聞社が責任をとることもせず、自らの力で解消する努力もせずに幕引きを図ることは、「押し紙」に苦しんできた無数の新聞販売店経営者のことを考えると、到底、許すことはできません。
零細な新聞販売店の経営者とそのご家族、従業員の方達の生活と人生を犠牲にして(自殺した販売店経営者がおられることを思うと、「生き血をすって」と表現した方がよいかもしれません。)巨額の利益をむさぼってきた新聞社の断末摩については、「押し紙」裁判の歴史とともに、きちんと記録に残しておくべきでしょう。
4月19日には読売新聞西部本社に対する別の「押し紙」訴訟の控訴審判決の言い渡しがあります。その結果は、後日また報告させていただきます。
引き続き、皆様のご支援のほどをよろしくお願いして、読売新聞大阪高裁判決の報告とさせて頂きます。
読売「押し紙」裁判、喜田村洋一(自由人権協会代表理事)らが勝訴判決の閲覧制限を申し立て、大阪高裁は3日付けで閲覧制限を認める

読売新聞「押し紙」裁判の続報である。読売の代理人を務める自由人権協会代表理事の喜田村洋一弁護士らが、大阪高裁判決(読売勝訴)の閲覧制限を大阪高裁に申し立てていたことが分かった。
これを受けて、読売勝訴の判決を執筆した大阪高裁の長谷部幸弥裁判長が、3日付けで、早々とそれを認める決定を下した。
閲覧制限が認められた記述の中には、読売の残紙の実態を摘示する箇所も含まれている。
読売新聞大阪本社に問い合わせ、判決文の黒塗り希望箇所を確認

大阪高裁は、28日、読売新聞「押し紙」裁判の控訴審判決で、控訴人の元販売店主の控訴を棄却した。詳細を解説するに先立って、読売新聞社(大阪)にある問い合わせを行った。
読売新聞は、このところ「押し紙」裁判の裁判書面に閲覧制限をかける動きを強めている。そのため読売に配慮するかたちで黒塗りを希望する箇所を問い合わた。読売がどの箇所の黒塗りを希望するか興味深い。
なお、この裁判には読売の代理人として、喜田村洋一・自由人権協会代表理事らがかかわっている。喜田村氏は、今世紀の初頭から一貫して読売新聞には1部の「押し紙」も存在しないと主張している。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
読売新聞大阪本社 法務部様
お世話になります。
フリーランスライターの黒薮哲哉です。
3月28日に貴社を被控訴人とする裁判(控訴人・濱中勇志)の判決が大阪高裁でありました。
つきましては判決の全文をウエブサイト等で公開することにしました。それに先立って、控訴人と被控訴人の双方に対して黒塗りを希望する箇所を確認しています。
控訴人からは、個人名と住所を黒塗りにしてほしい旨の希望がありました。
貴社に対しても、黒塗りにする箇所を提示していただきたく、ご連絡を差し上げました。
お手数ですが、添付しましたファイルを印刷して、非公開を希望する箇所を黒マジック等で黒塗りにするようにお願いします。全文非公開を希望されるようであれば、必ず全箇所を黒塗りにするようにお願いします。出来る限り、貴社の希望に沿うようにします。
3月3日の18時までに返信いただくようにお願い申し上げます。
黒薮哲哉
電話:048-464-1413
読売「押し紙」裁判控訴審、28日に判決

大阪高裁は、3月28日(木)の13:20分に702号法廷で、読売新聞「押し紙」裁判の控訴審判決を言い渡す。当初、判決は3月7日に予定されていたが、急遽、28日に変更になっていた。
大阪地裁での第一審判決は、読売が勝訴したが、裁判所は読売の独禁法違反を一部認めた。控訴審でそれが維持されるかどうかがひとつの注目点になっている。維持された場合、新聞業界への影響は甚大なので、裁判所がそれに配慮するのではないかという見方が販売関係者らの間で広がっている。
「押し紙」問題は1960年代にはすでに浮上しているが、今だに解決のめどは立っていない。インターネットで「押し紙」を検索すると、2500万件もの記述が確認できる。しかし、日本新聞業界と新聞社は、「押し紙」をしたことは一度もないと主張してきた。公正取引委員会も取り締まろうとはしない。日本のジャーナリズムの恥部にほかならない。
読売の代理人には、人権擁護団体のひとつである自由人権協会の代表理事を務めている喜田村洋一弁護士も名を連ね、読売に「押し紙」は1部も存在しないと主張してきた。
読売新聞「押し紙」裁判、判決日を3月28日に急遽変更、不自然な裁判の進行

大阪高裁は、3月7日に予定していた読売新聞(大阪)を被告とする「押し紙」裁判の判決日を、急遽延期した。新しく指定した判決日は、3月28日(木)の13:20分である。法廷は702号。
このところ「押し紙」裁判で物議をかもす現象が立て続けに起きている。判決の直前になって判決日が延期されたり、担当裁判官が交代する例が相次いている。いずれのケースでも、最終的に裁判所は、新聞社を勝訴させ販売店を敗訴させている。
「押し紙」裁判が公正に実施されていないのではないかという指摘は以前からあった。わたしもかねてから、この点に疑惑を持っている。
「押し紙」は、今や多くの人が知っている新聞社の汚点であり、しかもそれが半世紀以上も続いてきた。新聞販売店が内容証明で「押し紙」の買い取りを断っていても、損害賠償は認められない。なんとも不思議な現象が続いてきた。
公平な裁判と「押し紙」問題を考える上で、参考までに2つの重要文書を紹介しておこう。
【1】 下記のURLで確認できる文書は、公正取引委員会と新聞協会が、新聞の商取引について話し合ったときの議事録(1999年)である。情報公開請求で入手したものであるが、肝心な部分が黒塗りになっている。
わたしは、「押し紙」ついての公正取引委員会と新聞協会の話し合いの内容を記録した箇所の情報公開を請求したのだが、それに該当する箇所は全部黒塗りになっていた。従って、両者が何を話し合ったかは分からない。
http://www.kokusyo.jp/wp-content/uploads/2022/09/1ef02ee05325114bdb6d10e32b6a8402.pdf
わたしは「押し紙」問題の取り扱いに関して、公正取引委員会と新聞協会の間に密約があるのではないかと疑っている。
「押し紙」は、新聞社に想像以上に莫大な利益をもたらす。新聞1部の卸値を月額1500円とすれば、10部の「押し紙」で1万5000円の不正収入が生まれる。それが新聞社に入る。100部で15万円、1000部で150万円、1万部で1500万円である。
日本の権力構造の一部である公正取引委員会やそれを管轄する内閣府が、この莫大な金額に着目すれば、新聞社を世論誘導に利用することができる。「押し紙」を取り締まらない代わりに、新聞紙面の内容を暗黙のうちにコントロールできる。裁判所が「押し紙」を断罪しない事情がここにあるとわたしは見ている。
【2】 下記のURLで確認できる文書は、最高裁事務総局が開示した下級裁判所から最高裁に充てた裁判の報告書である。個々の裁判は独立しているように考えられているが、最高裁事務総局が指定した事件については下級裁判所が審理内容を最高裁に逐一報告する制度が存在することをこの文書は裏付けている。この種の裁判は、「報告事件」と呼ばれている。1部の元裁判官らが問題視している。
http://www.kokusyo.jp/justice/16651/
中央紙が被告となっている「押し紙」裁判が報告事件に指定されているという確証はないが、URLリンク先の文書が示すように少なくとも「報告事件」そのものは存在する。従って不自然な裁判の進行が繰り返されれば、一応は報告事件を疑ってみる必要がある。わたしは、最高裁事務総局の指示によって、「押し紙」裁判の判決の方向性が決められていると見ている。
読売新聞「押し紙」訴訟・控訴審判決期日のお知らせ

福岡・佐賀県押し紙訴訟弁護団 弁護士 江上武幸
正月早々、能登半島地震・日航機と海保の飛行機の衝突事故など、驚くニュースが次々と飛び込んでくる波乱の年明けとなりました。犠牲になられた方々やご遺族の方々に対し謹んでお悔やみを申し上げます。
読売新聞大阪本社を相手方とした「濱中押し紙訴訟」の大阪高裁判決の言渡期日は、3月7日(木)午後1時20分からと決まりました。また、読売新聞西部本社を相手方とした「川口押し紙訴訟」の福岡高裁判決の言渡期日は4月19日(金)午後1時10分からと決まりました。
濱中訴訟の大阪地裁判決は、濱中さんが販売店経営を開始した月の仕入れ部数の約半分が押し紙であることを認める画期的な判断を示しています。大阪高裁が引き続きこの押し紙を認めるかどうかが注目されます。
川口訴訟の福岡地裁判決は、川口さんが950部の減紙を申し出たのに対し読売新聞が減紙を認めなかった点について減紙拒否の押し紙は認めませんでした。福岡高裁が減紙拒否の押し紙であるとの判断を示す可能性は残されていると考えています。
それぞれの高裁の裁判官達が、独占禁止法新聞特殊指定の「押し紙禁止規定」についてどのような解釈を示すのか、全国的な関心を呼ぶ判決となることは間違いありません。
販売店経営者の方から、押し紙裁判を起こしてもどうせ新聞社には勝てないのでしょうと言われることがありますが、「やってみないとわかりませんよ。勝ち負けは裁判官次第ですから。」と答えています。
福井県の関西電力大飯原発運転差し止め判決を下した裁判官やパンツの裁判官で有名な裁判官もおられます。押し紙裁判でも、販売店が勝訴した判決や勝訴判決に等しい和解で解決した例もあります。
公正取引委員会や国会・裁判所等で押し紙問題が長い間取り上げられてきているにもかかわらず、何故、いつまでも解決しないのかといった疑問についての回答は、黒薮さんの押し紙問題シリーズの最新版「新聞の公権力の暗部『押し紙』問題とメディアコントロール」(鹿砦社刊)が答えてくれています。是非、ご購入されることをおすすめします。
最近、「一月万冊」・「金子吉友」・「原口一博(議員)」・「管理人のぼやきラジオ」などのネット番組をよく視聴するようになりました。これらの番組の主催者は、失われた30年といわれる日本社会の没落の原因は、日本がアメリカの半植民地である状態が戦後ずっと続いているためであるとの認識で一致しておられるように思われます。
黒藪さんにも、押し紙問題に限らず様々な分野の知識・経験をネット番組で全国に発信されることをおおいに期待しております。
高裁判決の結果については、判決が出てその内容を見てから報告させていただきます。
最後になりますが、昨年は多額の活動資金のご寄付をいただき有難うございました。重ねてお礼を申し上げます。ありがとうございました。
2023年7月度のABC部数、朝日364万部、読売630万部、夕刊廃止も時間の問題か?

2023年7月度のABC部数が明らかになった。それによると、朝日新聞は約364万部で、前年同月比で約-48万部だった。読売新聞は約630万部で、約-46万部だった。毎日新聞は約166万部で、約-23万部だった。
ABC部数の下落にまったく歯止めかかっていないことが明らかになった。詳細は次の通りである。
朝日新聞:3,636,675(-484,565)
毎日新聞:1,659,153(-226,010)
読売新聞:6,295,920(-464,491)
日経新聞:1,473,712(-230,103)
産経新聞:951,020(-62,663)
夕刊廃止の動きも顕著になっていて、たとえば9月1日から北海道新聞が夕刊を廃止した。夕刊廃止が中央紙に及ぶのは時間の問題となった。
読売新聞大阪本社の辣腕ジャーナリストに公開質問所を送付、「押し紙」問題についてジャーナリスト個人としての見解を求める

筆者は、8月10日、読売新聞大阪本社の柴田岳社長宛てに公開質問状を送付した。柴田社長は日経新聞によると、アメリカ総局長、国際部長、東京本社取締役編集局長、常務論説委員長などを務めた辣腕ジャーナリストである。
公開質問状の全文を読者に公開する前に、事件の概要を手短に説明しておこう。
発端は今年の4月20日にさかのぼる。大阪地裁は、読売新聞を被告とする「押し紙」裁判の判決を下した。判決は、原告(元販売店主)の請求を棄却する内容だったが、読売新聞の取引方法の一部が独禁法違反に該当することを認定した。「押し紙」の存在を認めたのである。
このニュースを筆者は、デジタル鹿砦社と筆者の個人サイトで公表した。その際に、判決文もPDFで公開した。ところが6月1日に読売新聞大阪本社の神原康之氏(役員室法務部部長)から、判決文の公開を取り下げるよう求める「申し入れ書」が届いた。それによると判決文の削除を求める理由は、文中に読売社員のプライバシーや社の営業方針などにかかわる箇所が含まれていることに加えて、同社が裁判所に対して判決文の閲覧制限を申し立てているからというものだった。他の裁判資料の一部についても、読売新聞は同じ申し立てを行っていた。
確かに民事訴訟法92条2項は、閲覧制限の申し立てがあった場合は、「その申立てについての裁判が確定するまで、第三者は、秘密記載部分の閲覧等の請求をすることができない」と規定している。
そこで筆者は判決文を一旦削除した上で、裁判所の判決を待った。しかし、裁判所は読売新聞の申し立てを認めた。公開を制限する記述を黒塗りにして提示した。
筆者は、黒塗りになった判決文を公開することを検討した。そこで念のために神原部長に、この点に関する読売新聞の見解を示すように求めたが、明快で具体的な回答がない。「貴殿自身にて、弊社の営業秘密や個人のプライバシーを侵害しないように十分にご留意頂き、ご判断ください」(6月28日付けメール)などと述べている。読売側の真意がよく分からなかった。
そこで筆者は、読売新聞大阪本社の柴田岳社長に公開質問状を送付(EメールによるPDFの送付)したのである。公開質問状の全文は次の通りである。
《公開質問状の全文》
2023年8月10日
公開質問状
大阪府大阪市北区野崎町5-9
読売新聞大阪本社
柴田岳社長
CC: 読売新聞グループ本社広報部
発信者:黒薮哲哉(フリーランス・ジャーナリスト)
電話:048-464-1413
Eメール:xxxmwg240@ybb.ne.jp
貴社が2023年の4月21日、大阪地裁で手続きを行った訴訟記録の閲覧制限申し立て事件についてお尋ねします。
貴社から訴訟記録の閲覧制限の申立を受けた大阪地裁は、同年6月5日付で、当事者以外の者が、判決文を含む28通に及ぶ文書の内、貴社が公開を望まない部分についての閲覧・謄写、正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製を請求することを禁止する決定を言い渡しました。貴社が閲覧制限を求めたのは、貴社の残紙の規模を示す購読者数と仕入れ部数(定数)との誤差がわかる部数や、押し紙行為の実態が判明する取引現場における原告と販売局幹部や担当との生々しいやり取りが記録された箇所がメインです。
そこで、以下の点について質問させていただきます。
1,まず、判決理由中に、「実配数を2倍近く上回る定数」の新聞を貴社が原告対し注文部数として指示した事実が認められています。つまり、原告が経営していたYCでは、搬入される新聞の約50%が残紙であったことを裁判所が認めました。新聞ジャーナリズムの信用にかかわるこのような重大な司法の判断が下されたことに対し、貴社はどのように考えておられるでしょうか。読売新聞社としての見解と、ジャーナリストとしての貴殿個人の見解を回答ください。
2,「押し紙」問題は1980年ごろから、その深刻な実態がクローズアップされてきました。販売店の残紙の性質が「押し紙」なのか、それとも「積み紙」なのかの議論は差し置き、貴社の発行部数の中には、膨大な量の残紙が存在してきたことは紛れもない事実です。貴社が閲覧制限の対象とした判決文にも、2012年4月時点で、定数の内、約半分が購読者のいない残紙であることが記載されています。わたしが、このような押し紙裁判史上画期的な司法判断を示した大阪地裁判決を、判断の資料となった当事者双方の主張書面や書証、引いては公開の法廷における証人尋問調書等を含めて公開することにより、貴社に、どのような不利益が生じるのかを具体的に教えてください。抽象論ではなく、具体的に教えてください。
3,わたしが、大阪地裁の画期的な司法判断を広く社会に報じるにあたり、裁判官の判断の裏付けとなった当事者の主張書面や証拠や判決文全部を読者に示す必要があります。つまりこの問題を報じる側に身を置かれた場合、貴社や貴殿は、黒塗りされた判決文と閲覧謄写が禁止された訴訟記録で、どのようにして読者に対し真実を正確に伝えることが出来るとお考えですか。読売新聞社としての見解と、ジャーナリストとしての貴殿個人の見解を教えてください。
4,判決文を含む訴訟記録に閲覧制限をかけた場合、ジャーナリズムの取材活動や学術研究活動にも重大な支障が生じますが、押し紙裁判資料の公共性・歴史的意義についてどのようにお考えでしょうか。読売新聞社としての見解と、ジャーナリストとしての貴殿個人の見解を教えてください。
5,貴社は今後、「押し紙」裁判の訴訟記録を閲覧制限が認められた箇所を含め、全部公開する意思がおありでしょうか。公開する予定があるとすれば、その時期を教えてください。それとも閲覧制限が認められた箇所は、永久に封印する方針なのでしょうか。
以上の5点をお尋ねします。回答は、2023年8月21日までにお願いします。
【投稿】読売新聞は何を恐れているのか 、―判決文の閲覧制限申立に関して―

執筆者:江上武幸(弁護士)
既報のとおり、読売新聞大阪本社と西部本社は、一審で全面勝訴判決を受けたにもかかわらず、判決文の閲覧制限の申立を行いました。読売が閲覧制限を求めたのは、原告販売店の購読部数や供給部数が記載された個所です。
当事者以外の第三者、例えば、新聞や週刊誌の記者、フリーのジャーナリスト、大学の学者・研究者等が、押し紙問題を調査報道し、研究発表するために判決の閲覧謄写を請求しても、肝腎の部数については黒塗りした判決文しか入手できないことになります。もちろん、全面開示を求める訴えをする道は残されていますが、そのためには多大な労力と時間と経費を費やす覚悟が求められます。
国民にかわって憲法上の知る権利を行使する使命を担う新聞社が、自社を当事者とする裁判の判決について閲覧制限を求めるという身勝手な姿勢を示したことは、厳しく非難されるべきです。
押し紙問題はインターネット上ではすでに公知の事実となっており、何ら隠しだてするところはありません。
そうは言っても、押し紙裁判の被告になった新聞社が、判決に購読部数と定数が記載されておれば、ABC部数(公表部数)や折込広告部数がいかに実態とかけ離れた部数であるかが一目瞭然となるため、その部数を知られないよう判決の閲覧制限を求める誘惑に駆られることはあり得ることです。しかし、良識を備えた新聞社であれば、自社の利益と国民の知る権利及び裁判の公開の原則を天秤にかけた場合、後者を優先すべきであるとの判断を下すのは当然のことです。
押し紙裁判を提訴する原告は、購読部数と定数(供給部数)を整理した別紙「押し紙一覧表」を作成して訴状に添付するのが一般的です。しかし、訴状に添付した資料と裁判所が判決に添付した資料の重みは決定的に違います。
押し紙問題に関心を寄せる公正取引委員会やABC協会、国会議員あるいは大学の学者・研究者等は、判決に購読部数と供給部数が明示されておれば、裁判で争われた販売店の押し紙の実態を正確に知ることが出来、各々の立場で押し紙問題を分析し解決の方向を指し示すことができます。
ちなみに、黒藪さんは、読売新聞社以外の新聞社で、判決文の閲覧制限を申し立てた例があるかどうか調査してみるとのことです。
どの業界にも超えてはならない一線があります。新聞社にとって、判決文の閲覧制限を申し立てるのは言論機関にあるまじき一線を越えた暴挙といって差し支えないでしょう。
読売新聞は発行部数1000万部の世界一の新聞であることを豪語してきましたが、2007年(平成19年)6月の真村福岡高裁判決以降、福岡県内の複数の読売新聞販売店から押し紙問題の相談を受けた私の経験では、当時、すでに3割から5割近い部数が読者のいない新聞で占められていました。
日本特有の宅配制度のもとで、読売新聞に限らず多くの新聞社は優越的地位を濫用し、実際の購読部数よりはるかに多い新聞を販売店に買い取らせる「押し紙」を行ってきました。「押し紙」は我が国の新聞社の「ビジネスモデル」であると評されたことがあるほどです。
新聞社がこのような有様ですから、日本に民主主義の精神が根付かなかったのもむべなるかなと思います。
他方、押し紙問題の解決に真摯に取り組んだ新聞社が多数あることも指摘しておく必要があります。私の知る限りでは、熊本日々新聞社と新潟日報社は独占禁止法を忠実に守って押し紙とは無縁の新聞社経営を行ってきています。ほかにも同じような新聞社があると思います。このような新聞社があることを知ることが出来たことは救いです。
私は、わが国のモラル崩壊の元凶は小選挙区制と新聞の押し紙にあると確信をもっていえるようになりました。また、最近では押し紙裁判の担当裁判官の意図的ともいうべき人事配置の問題についても歴史に刻んでおく必要があると感じるようになっております。そのことに踏み込む力量は持ち合わせていませんが、ユーチューブの報道番組を見ていると、かっての新聞記者を凌駕する知性と情報発信力の持ち主が多数活躍されており、その中の誰かが司法の闇に切り込んでくれることを期待しているところです。【2023年(令和5)7月5日】
「営業秘密」の中身を解明する作業が不可欠、読売が申し立てた「押し紙」裁判の判決文に対する閲覧制限事件⑤

濱中裁判(読売を被告とする「押し紙」で、読売が勝訴。原審は大阪地裁)の判決文に対して読売が閲覧制限をかけ、それを野村武範裁判官が認めた件に関する続報である。この判決をメディア黒書で公開するに際して、読売に対して黒塗り希望箇所を問い合わせていたところ、29日の夕方に回答があった。
本来であれば、回答の全文を公開するのがジャーナリズムの理想であるが、読売側がそれを嫌っているので、回答のポイントをわたしの言葉で説明しておこう。ポイントは次の2点である。
❶読売は民事訴訟法92条を根拠に、判決文の閲覧制限を申し立てた。92条は次のように述べている。
第92条
次に掲げる事由につき疎明があった場合には、裁判所は、当該当事者の申立てにより、決定で、当該訴訟記録中当該秘密が記載され、又は記録された部分の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製(以下「秘密記載部分の閲覧等」という。)の請求をすることができる者を当事者に限ることができる。
一 訴訟記録中に当事者の私生活についての重大な秘密が記載され、又は記録されており、かつ、第三者が秘密記載部分の閲覧等を行うことにより、その当事者が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあること。
二 訴訟記録中に当事者が保有する営業秘密(不正競争防止法第2条第6項に規定する営業秘密をいう。第132条の2第1項第三号及び第2項において同じ。)が記載され、又は記録されていること。
前項の申立てがあったときは、その申立てについての裁判が確定するまで、第三者は、秘密記載部分の閲覧等の請求をすることができない。
秘密記載部分の閲覧等の請求をしようとする第三者は、訴訟記録の存する裁判所に対し、第1項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至ったことを理由として、同項の決定の取消しの申立てをすることができる。
第1項の申立てを却下した裁判及び前項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
第1項の決定を取り消す裁判は、確定しなければその効力を生じない。
❷読売は、黒塗り希望箇所を提示するように求めているわたしの要求に対して、回答を控えると回答してきた。その理由として次のように述べている。「弊社の見解は、弊社の閲覧等制限の申立て及び裁判所の決定内容に含まれ、それ自体が営業秘密にかかわる事項になりますので、(訴訟当事者ではない第三者である貴殿に)弊社からお答えすることは控え」る。
細かい指摘になるが、引用した文章は論理が曖昧でどうにでも解釈できる余地がある。達意という作文の機能をはたしていない。閲覧制限の申立書と野村裁判官が下した決定内容に、閲覧制限の範囲(黒塗りの箇所)についての読売の見解が含まれており、それ(黒塗りの部分)自体が「営業秘密にかかわる事項」なので、回答できないと述べているのだが、この記述だと、読売が提出した申立書はいうまでもなく、判決文の中のどの箇所が黒塗りになっているかも「営業秘密」になるという解釈になってしまう。つまり申立書と判決の全文の非公開を求めているように解釈できる。しかし、裁判所は、黒塗りにした箇所以外は公開していると説明している。
◆今後の対応
ただ、「営業秘密」の中身が具体的な販売政策を指している可能性もあるので、❶と❷を踏まえた上で、わたしは読売の法務部へ次のように再質問をした。
文中にある「営業秘密」とは、具体的に何を指しているのかをご説明ください。たとえば部数内訳のことを言っているのか、補助金制度の運用方法のことを言っているのかなどをご説明ください。どうにでも我田引水に解釈できるようであれば、文書で意思疎通を図る意味がありません。揚げ足取りの原因になります。
わたしが読売からの回答の細部にこだわるのは、2008年に当時の法務室長が、自由人権協会代表理事の喜田村洋一弁護士と協働して、わたしに対してとんでもない裁判を起こした過去があるからだ。それがどのような事件であったかは、次の転載記事を参考にしてほしい。若干長くなるが、判決文も含めて全文を引用しておこう。
なお、読売が「営業秘密」の箇所を具体的に提示しないのであれば、わたしとしては他のジャーナリストとも共同して、野村裁判官が下した判決の取り消しを裁判所へ申し立てざるを得ない。というのも、濱中裁判では読売による独禁法違反は認定されており、「営業秘密」の中に、あるまじき行為が含まれている可能性もあるからだ。
【転載記事】読売・喜田村洋一・自由人権協会代表理事らによる口封じ裁判から9年目に、今後も検証は続く(2016年12月20日付け)
江崎氏の申し立ては、わたしがメディア黒書に掲載した江崎名義の1通の催告書の削除を求めるものだった。しかし、江崎氏は法務室長という立場にあり、実質的には、江崎氏個人ではなく、読売新聞社との係争の始まりである。
事実、その後、読売から3件の裁判、わたしから1件の裁判と弁護士懲戒請求を申し立てる事態となった。
◇真村事件から黒薮裁判へ
この裁判の発端は、福岡県広川町にあるYC広川(読売新聞販売店)と読売の間で起こった改廃(強制廃業)をめぐる事件だった。当時、わたしは真村事件と呼ばれるこの裁判を熱心に取材していた。
係争の経緯については、長くなるので省略するが、2007年の12月に真村氏の勝訴が最高裁で決定した。日本の裁判では、地裁と高裁で連勝すれば、最高裁で判決が覆ることはめったにない。そのために最高裁の判断を待つまでもなく、高裁判決が出た6月ごろから真村氏の勝訴確定は予想されていた。
そのためなのか、読売も真村氏に歩み寄りの姿勢を見せていた。係争になった後、中止していた担当員によるYC広川の訪店を再開する動きがあった。そして江碕氏は、その旨を真村氏に連絡したのである。
しかし、読売に対して不信感を募らせていた真村氏は即答を控え、念のために代理人の江上武幸弁護士に相談した。訪店再開が何を意味するのか確認したかったのだ。江上弁護士は、読売の真意を確かめるために内容証明郵便を送付した。これに対して、読売の江崎法務室長は、次の書面を返信した。
前略 読売新聞西部本社法務室長の江崎徹志です。
2007年(平成19年)12月17日付け内容証明郵便の件で、訪店について回答いたします。当社販売局として、通常の訪店です。
わたしは、メディア黒書で係争の新展開を報じ、その裏付けとしてこの回答書を掲載した。何の悪意もなかった。むしろ和解に向けた動きを歓迎していた。
しかし、江崎氏(当時は面識がなかった)はわたしにメールで次の催告書(PDF)を送付してきたのである。
冠省 貴殿が主宰するサイト「新聞販売黒書」に2007年12月21日付けでアップされた「読売がYC広川の訪店を再開」と題する記事には、真村氏の代理人である江上武幸弁護士に対する私の回答書の本文が全文掲載されています。
しかし、上記の回答書は特定の個人に宛てたものであり、未公表の著作物ですので、これを公表する権利は、著作者である私が専有しています(著作権法18条1項)。 貴殿が、この回答書を上記サイトにアップしてその内容を公表したことは、私が上記回答書について有する公表権を侵害する行為であり、民事上も刑事上も違法な行為です。
そして、このような違法行為に対して、著作権者である私は、差止請求権を有しています(同法112条1項)ので、貴殿に対し、本書面到達日3日以内に上記記事から私の回答を削除するように催告します。
貴殿がこの催告に従わない場合は、相応の法的手段を採ることとなりますので、この旨を付言します。
わたしは削除を断った。先に引用した、
前略 読売新聞西部本社法務室長の江崎徹志です。
2007年(平成19年)12月17日付け内容証明郵便の件で、訪店について回答いたします。当社販売局として、通常の訪店です。
と、いう回答書は著作物ではないからだ。催告書の形式はともかく、書かれた内容自体はまったくのデタラメだった。著作権法によると、著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」。上記の回答書は、著作物ではない。催告書の内容そのものが間違っている。
そこで、今度はこの催告書をメディアで公開した。これに対して、江崎氏は、催告書は自分の著作物であるから、著作者人格権に基づいて、削除するように求めてきたのである。
そして喜田村弁護士を立てて、催告書の削除を求め、仮処分を申し立てたのである。(回答書の削除は求めてこなかった。)
こうして江崎氏名義の催告書が、著作物かどうかが争点となる係争が始まったのだ。書かれた内容の評価とは別に、催告書が著作物かどうかという点に関しては、一応は議論の余地があった。書かれている内容そのものがデタラメであっても、それに著作物性があるかどうかは、別問題である。
結論を先に言えば、仮処分申立は、江崎氏の勝訴だった。催告書が著作物と認めれらたのだ。
判決に不服だったわたしは、本訴に踏み切った。代理人は江上弁護士ら、真村裁判の弁護団が無償で引き受けてくれた。わたしは東京・福岡間の交通費もふくめて、1円の請求も受けなかった。
◇重大な疑惑の浮上
本訴の中で重大な疑惑が浮上した。
既に述べたように、この裁判は、江崎氏が書いたとされる奇妙な内容(例の回答書が著作物であるという内容)の催告書が争点だった。内容が奇妙でも催告書が江崎氏の著作物であると認定されれば、わたしは削除に応じなければならない。
仮処分では負けたわたしだが、裁判の途中から様相が変わってきた。特に江崎本人尋問を機に流れが変わった。
確かに催告書の名義は江崎氏になっているが、催告書は喜田村弁護士が作成したものではないかという疑惑が浮上してきたのだ。
著作者の権利は、著作権法では、「著作者人格権(公表権などが含まれる)」と「著作者財産権」に別れるのだが、前者は他人に譲渡することができない。一身専属権である。
江崎氏は、著作者人格権を根拠に、わたしを提訴したのである。と、なれば江碕氏が催告書の作者であることが、提訴権を行使できる大前提になる。仮に他人が書いたものなら、それはたとえば、わたしが村上春樹氏の作品を自分のものだと偽って、著作者人格権による権利を求める裁判を起こすのと同じ原理である。
催告書の本当の作成者が喜田村弁護士だとすれば、喜田村氏らは催告書の名義を「江碕」偽り、それを前提にして、著作者人格権を主張する裁判を起こしたことになる。
◇東京地裁・知財高裁の判決
東京地裁は、わたしの弁護団の主張を全面的に認めて、江崎氏の訴えを退けた。喜田村洋一弁護士か、彼の事務所スタッフが催告書の本当の作者である可能性が極めて強いと認定したのである。
このあたりの事情については、地裁判決直後の弁護団声明を参考にしてほしい。弁護団は、この事件を「司法制度を利用した言論弾圧」と位置づけている。
次の引用するのは、知財高裁判決の重要部分である。催告書の名義人偽り疑惑について、次のように言及している。
上記の事実認定によれば、本件催告書には、読売新聞西部本社の法務室長の肩書きを付して原告の名前が表示されているものの、その実質的な作者(本件催告書が著作物と認められる場合は、著作者)は、原告とは認められず、原告代理人(又は同代理人事務所の者)である可能性が極めて強い。
繰り返しになるが、江崎氏は、元々、著作者人格権を主張する権利がないのに、催告書の名義を「江崎」に偽って提訴し、それを主張したのである。
喜田村弁護士は、自分の行為が弁護士としてあるまじき行為であることを自覚していたはずだ。弁護士職務基本規定の第75条は、次のようにこのような行為を禁止している。
弁護士は、偽証若しくは虚偽の陳述をそそのかし、又は虚偽と知りながらその証拠を提出してはならない。
ところが名義を偽った催告書を前提にして、裁判所へ資料を提出し、自己主張を展開したのだ。
裁判が終わった後、今度はわたしの方が攻勢に転じた。喜田村弁護士が所属する第2東京弁護士会に対して、喜田村弁護士の懲戒請求を申し立てた。2年後に、申し立ては却下されたが、多くの法律家が前代未聞のケースだとの感想を寄せた。弁護士会の判断は誤りだと話している。現在、再審を検討している。曖昧な決着はしないのが、わたしの方針だ。
今後も検証は続く。