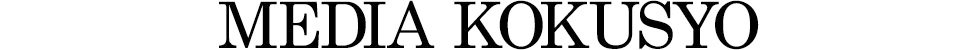デッチ上げまでする裁判官 狙いは戦前の報道弾圧社会への回帰
◆吉竹幸則(フリージャーナリスト・元朝日新聞記者)
前回、前々回とこの欄で、「公正・公平性を失った司法」について書いた。「裁判官が本当にデッチ上げまでするのか」「筆者が裁判に負けた腹いせではないのか」こんな疑問の声も戴いた。
ジャーナリストが語るべきは、論より事実だ。私事で恐縮になるのを承知で、敢えて私の朝日新聞社への訴訟の判決を紹介してみたい。
いかに裁判官が、露骨なデッチ上げ判決までするようになったか。今の司法・裁判所がジャーナリズムから「表現・報道の自由」を奪い、戦前の報道弾圧社会の再来を、どんなにしゃかりきになって目指しているか。読売から訴えられた黒薮哲哉氏の最高裁逆転判決とともに、私への判決がその典型的な事例の一つと思えるからだ。
◆公共事業の利権を隠蔽
なぜ、裁判官の監視が必要なのか。読者の方々に、「公正・公平さを失った今の司法・裁判所の実態」を、より具体的に分かって戴きたいのだ。
私が何を取材し、朝日がその記事をどう止めたか。拙書『報道弾圧』(東京図書出版刊)では詳しく書いている。ここでそのすべてを書く字数の余裕はない。
「ダム・無駄な公共事業」は古くて新しい問題だから、いずれはこの欄でもう少し詳しく説明しようと思う。今回はごくごく簡単に紹介することに留める。 私が書こうとしていたのは、当時、無駄な公共工事の典型として、住民から激しい反対運動が繰り広げられていた長良川河口堰についての記事だった。建設省(現国交省)の着工理由は「治水のため」。
でも、これは全くのウソ。後述する名古屋高裁判決でも認めている通り、私が入手した同省の極秘資料を使い行政マニュアル通りに計算しても、長良川に堰がなくても、想定される最大大水で堤防下2メートルの安全ラインよりさらに下しか水は来ない。
記事は、緻密な取材でそれを裏付け、科学的に「無駄」を立証するものになるはずだった。
「自然保護」か「治水」かと言った、主観的な感情の入る記事ではない。人々の「知る権利」に応えなければならない報道機関なら、当然、この事実を報じる責務がある。でも、朝日は何らまともに理由も告げず、記事を止めた。
◆「裁量権の濫用」は違法行為
もちろん私は、編集局長に異論を唱えた。しかし、朝日は聞く耳を持たず、逆に報復として私から記者職を剥奪した。
朝日には、記者として当然の責務を果たそうとした私に対する不当差別待遇と、ブラ勤で職場のさらし者にするなどの名誉毀損がある。訴訟は、その行為による逸失利益、慰謝料などの損害賠償を朝日に求めるものだった。
不当待遇か否かを争う労働訴訟では、法学部の学生でも知っている「不利益変更法理」と言う有名な最高裁判例が基本的な尺度になっている。
雇用主は雇用者に対し、人事、査定などの裁量権がある。でも、何をやっても許されると言うものではない。法理では、職場実態、労働慣行など具体的事実に照らし、「業務上の必要性が存しない場合」「他の不当な動機・目的をもってなされたとき」「労働者に対し通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものであるとき」には、雇用主の「裁量権の濫用」に当たる。
別職種への配転など雇用者の労働条件を不利益なものに変更する場合、この3条件に抵触していないかを基準に、人事・査定の合理性についての「高度な説明責任」もある。雇用主がその義務を果たしていない場合も、不法行為や債務不履行が成立するとしている。
朝日は何故、私の記事を止め、記者職を剥奪、昇格・昇給でも差別したか。在職中、私は何度も文書で説明を求めて来た。しかし、朝日は何の合理的な説明もしていない。
つまり、人事・処遇の「不利益変更」理由について「説明責任」を果たしていないから、この法理に基づけば、「朝日には裁量権の濫用がある」と言うのが、私の主張だ。
◆裁判官による巧みな論点のすり替え
名古屋地裁の1審で私は、職場実態・慣行に照らし、「濫用」の有無を具体的に事実審理するよう、繰り返し求めた。だが、裁判官は一切拒否。本人尋問で私の言い分を聞くことさえせず、早々と審理を打ち切った。
そして、提訴から半年余りの2009年4月の判決では、具体的な「濫用」の有無に触れず、「報道価値のある記事に該当するか否かは経営管理者が編集方針に照らし、裁量的判断によって決定すべき事柄である」として、私を敗訴にした。
つまり、裁判官の判断は、記者が何を取材し何を書いたとしても、編集権は経営者にあるから、記事にして載せるか否かは経営者の勝手気まま、記者が文句をつける筋合いではない。記者の職に就けるのも、外すのも経営者の自由と言うことのようなのである。
私が朝日の「名誉毀損」として訴えた内容に、裁判官がどう判断したかも触れておこう。
判決では、「面談で原告(私)が,編集局に記者として復帰したい旨述べたのに対し、名古屋本社代表がデスクらとの信頼関係を取り戻すことの必要性を指摘したことが窺えるものの、それだけでは名誉毀損の不法行為を構成するものとはいえず、それ以上の状況や発言内容を認めるに足りる証拠はない」としている。
私が朝日の「名誉毀損」と裁判官に訴えたのは、?記者の職を剥奪し、ブラ勤で私を社内のさらし者にした行為?私が組織のあり方を社内ネットで質した際、ありもしないのに「評価や人事にめぐる不満については、それを取り扱う所定のルートがあります」と、あたかも私が社内ルールを逸脱した人物かのような虚偽の事実をネットで公開したこと――に対してである。
「名誉毀損」は、公開の場での中傷・虚偽発言などで人の名誉を傷つけられた場合に成立する。私に対して名古屋代表が密室で発した言葉で、もともと「名誉毀損の不法行為を構成するもの」とは言えないのは当たり前なのだ。
私が「名誉毀損」と提示した事実に一切触れず、もともと「名誉毀損」が成立しない問題を裁判官が勝手に持ち出し、「名誉毀損の不法行為を構成するものとはいえず」では、聞いてあきれる。私を敗訴させることだけを目的とした「すり替え判決」としか、言いようがないのだ。
経営者に裁量権の逸脱があったか否かは、具体的事実に基づいて判断するのが「不利益変更法理」の基本的な考え方だ。裁量権逸脱の有無について、事実審理を全くしていない地裁判決は、この最高裁判例に違反する。「名誉毀損」も論点のすり替えだから、判決に値しない。私は、不当判決の理由を詳しく書き、控訴した。
ところが、極め付きは名古屋高裁民事3部(高田健一裁判長)のデッチ上げ判決だった。高裁でも、私が再三求めた事実審理や本人尋問さえ一審同様、一切拒否。第1回口頭弁論で審理を打ち切ったにも拘らず、突然判決文で事実認定に踏み込んだ。
◆裁判長による恐るべき改ざん
河川工学の専門用語も出てくるから難解で少し長いが、判決文を引用してみたい。
「(ア)1990年6月ころまでに、長良川河口堰に関する取材を完了し、その取材によっておおむね以下のとおりの取材結果を新聞記事とすることを求めた。政府は、長良川河口堰建設にあたり、治水、利水を区別することなく3200万トンの浚渫が必要との閣議決定をしたが、建設省は、治水上1500万トンの土砂浚渫で足りることを知っていたこと、
建設省は、水余りが明らかになるにつれて、利水から治水へと河口堰建設目的の重点を移し、長良川安八、墨俣水害の後、建設省自身で策定した『河川砂防技術基準』(行政マニュアル)に沿って長良川の粗度係数の値を算出し、この値に基づいて当時の最新河床データを使い、前記基準どおりに水理計算をすれば、建設省が長良川で想定している最大大水時においても、その水量は安全水位以下に収まり、少なくとも河口堰のような大規模な治水施設は必要のないことを十分承知していながら、前記粗度係数の値は低すぎたとし、
この係数でシミュレーションした結果を公表せず、根拠のない洪水の危険を吹聴して河口堰建設着工への機運を盛り上げたこと、河口堰建設反対運動の高まりと水需要の減退に伴い、本来なら、治水目的での必要浚渫量を1500万トンとして河口堰建設の是非を検討すべきであるのに、建設省はこれをせず、
また、前記基準では当時の最新河床データと安八水害で判明した現況粗度係数を使用すべきであるのに、古い河床データと計画粗度係数の値で計算した水位図を使用して、現状の長良川のままでは洪水の危険があるというデータを作り上げたこと、控訴人(私)の前記取材に慌てた建設省は、控訴人への取材対策として粗度係数を改ざんするなどの工作をして、長良川河口堰建設が、治水上、不要であったことを隠蔽したというものである」
「(イ) 当時の被控訴人(朝日)名古屋本社社会部デスクらが、控訴人の原稿を検討した結果、原稿記載のうち、ある水理工学者に不等流計算を依頼した結果、計画高水量(毎秒7500トン)の出水でもほとんどの地点で計画高水位を下回り、わずかに上回るところでも最大23センチメートルのオーバーで、この程度なら堤防のかさ上げなどで対応でき、わざわざ河口堰を作る必要はないのではないかという点については、不等流計算をし、その分析をした専門家の名前を新聞紙上で明らかにできない以上、朝日新聞の責任で前記計算を明らかにすることになるが、
それは、今後水害が起きたときのことなどを考えると、危険が大きすぎること、建設省の計算と前記専門家との計算の結果の違いが大きすぎるが、建設省も役所である以上、このような無茶な嘘をつくとは考え難いこと、控訴人の取材による計算も完全な専門家とはいえない者による計算であるから、計算データが抜け落ちている等の問題がないとはいえないこと、
少なくとも、もう少し慎重に建設省がどのような方法で計算をし、記者発表をしたのかを見極める必要があるとの意見が出され、控訴人に対し、建設省側に情報がある程度漏れることを覚悟のうえ、もう少し学者の意見を聞くとともに、実名で計算結果を発表してくれる学者がいないか探すこと、少なくとも、前記専門家の計算結果が、水理学的に正しいとのコメントを出してくれる学者などを探すこと,
建設省がどのような計算をし、記者発表をしたのか、これまでのルートを通じてさらに深く探れないか慎重に詰めるようにとの指示がなされた。しかしながら、控訴人がさらに取材をしたものの、実名で計算結果を発表してくれる学者は見つからなかった」
「以上認定の事実によれば、1990年頃、控訴人の取材結果は、社会部デスクによる検討の結果、水理計算に関するデータに抜け落ちている部分があるのではないかなどの疑問点が指摘され、その後の控訴人の取材によってもデスクから指摘された様々な疑問点が払拭されなかったために掲載が見送られたものであって、このような被控訴人の措置は、編集権の行使として相当なものと認められ、本件証拠上裁量権の濫用を基礎づける事情は見当たらない」
◆「4月」を「6月」に改ざん
河川工学の難しい用語は、別の機会に解説するから、読み飛ばしてもらえばいい。建設省がいかにウソで固めて河口堰を着工したか。私の取材・提出証拠により、高裁が(ア)で、事実として認定していることは分かって戴けると思う。
問題は(イ)である。「社会部デスクらが、控訴人の原稿を検討した」のは、「1990年」であっても、判決文にある「6月」ではなく、「4月」である。
つまり、「社会部デスク」の出した「建設省がどのような計算をし、記者発表をしたのか」の「疑問点」を、私が再取材で完全に解明した結果が(ア)なのだ。(ア)が分かっているなら、デスクは(イ)のような疑問を出すはずがない。判決の矛盾は明らかだ。
実際の時系列は(ア)→(イ)ではなく、(イ)→(ア)である。真実に基づいて、私が試しに判決文を書いてみると、結論部分は次のようにならざるを得ない。
「以上認定の事実によれば、1990年4月、控訴人の取材結果は、社会部デスクによる検討の結果、水理計算に関するデータに抜け落ちている部分があるのではないかなどの疑問点が指摘され、その後、控訴人の6月までの取材によって、(ア)の通り、様々な疑問点が払拭・解明されており、掲載が見送られる理由はなかった。にも拘わらず、記事を止めた被控訴人の措置は、編集権の行使として正当なものとは認められず、本件証拠上裁量権の濫用は明らかである」
◆裁判所はなぜ朝日を勝訴させたのか?
では、そんなデッチ上げ判決を、わざわざ裁判官が何故する必要があったのか、と読者は思われるだろう。しかし、権力にとって、不正・腐敗を嗅ぎまわる記者は、うるさい存在である。出来ればいなくなって欲しいと、本音では考えてもいるはずだ。国家権力・権力者の恥部を嗅ぎ回るのは、「悪い記者」であり、そんな記者の原稿をボツにするのは、「良い新聞経営者」である。
私の主張に沿い、「悪い記者」個々が取材した事実を記事にする権利を裁判所が認めてしまえば、「良い経営者」による報道の抑止は効かなくなる。いざという時、戦前社会と同様、経営者を抑えて報道弾圧を可能にしておくには、「編集権は独占的に経営者にあり、記者には何の権利もない」との朝日の主張ほど好都合なものはない。
権力に忠実なヒラメ裁判官なら、朝日の言い分にすんなり乗って戦前同様の報道規制の道を開いてしまおうと思っても何の不思議もないのだ。
だが、私から提出された証拠に基づき、事実審理や本人尋問を行い、実際の事実を解明してしまうと、「不利益変更法理」に照らし、私が試しに書いた判決文しか書きようがない。それでは「悪い記者」を勝訴させ、報道規制の道は開けない。
私を強引に敗訴させ、「悪い記者」の権利を否定するには、事実審理を一切せず、 (イ)→(ア)の時系列を 勝手に(ア)→(イ)に入れ替え、「取材不足があったから、記事にならなかった」との判決文を書くしかない。そう考えて裁判官が一切の事実審理を拒否、このデッチ上げ判決に手を染めたと考えると、すべての辻褄は合う。それ以外の理由も見当たらない。
私が「すり替え」として高裁に見直しを求めた「名誉毀損」の判断も、私の主張には一切触れず、一審判決をただコピーしただけ。
しかし、意図的な事実のデッチ上げをすれば、当然判決文は矛盾だらけになる。つまり上告理由に該当する「判決理由の食い違い」はいくらでもある。私は「食い違い」を幾つも挙げ、最高裁に上告した。
しかし、最高裁も一切審理をしなかった。そして、「上告理由は、違憲及び理由の不備、食い違いを言うが、その実質は、事実誤認、又は単なる法令違反を主張するものであり、事由に該当しない」とだけ書いて、私の主張を退けた。それ以上詳しく書くと、下級審の判決のボロが出てしまうからだろう。
◆報道弾圧社会再来の危険な兆候
改めて、私の訴訟と黒薮VS読売訴訟とを比較してもらいたい。黒薮氏のネット記事の中の些細な事実誤認に対しても最高裁はわざわざ審理をし直した。そして黒薮氏の「名誉毀損」を認め、「表現・報道の自由」をさらに縛ろうとした。
私の対朝日訴訟では、下級審から最高裁まで一貫して「表現・報道の自由」を守ろうとした私の主張に一切耳を貸さず、事実審理や本人尋問さえ拒否。挙句に露骨な「デッチ上げ」や「すり替え」判決までして、人々の「知る権利」を応えようとする記者の権利を認めず、敗訴させた。
裁判所が強引に勝訴させたのは、読売、朝日ではある。でも、人々の「知る権利」「表現・報道の自由」を守る側の主張ではない。共通するのは、権力側には都合のいい「報道弾圧」に迎合する主張だったからである。
これで、今の司法・裁判所がいかに公正・公平さを失っているか、ジャーナリズムから「表現・報道の自由」を奪い、戦前の報道弾圧社会の再来をしゃかりきになって目指しているのか、なぜ今、裁判官の監視が必要なのかを読者の方々に具体的に分かって戴けたのではないかと思う。私は裁判に負けた「腹いせ」で言っているのではない。
≪筆者紹介≫ 吉竹幸則(よしたけ・ゆきのり)
フリージャーナリスト。元朝日新聞記者。名古屋本社社会部で、警察、司法、調査報道などを担当。東京本社政治部で、首相番、自民党サブキャップ、遊軍、内政キャップを歴任。無駄な公共事業・長良川河口堰のウソを暴く報道を朝日から止められ、記者の職を剥奪され、名古屋本社広報室長を経て、ブラ勤に至る。記者の「報道実現権」を主張、朝日相手の不当差別訴訟は、戦前同様の報道規制に道を開く裁判所のデッチ上げ判決で敗訴に至る。その経過を描き、国民の「知る権利」の危機を訴える『報道弾圧』(東京図書出版)著者。